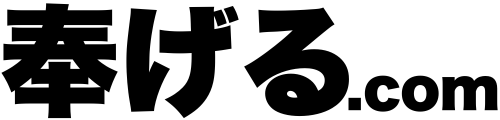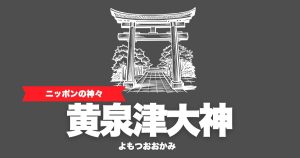高御産巣日神は、日本の神話で二番目に現われた神様です。生命の誕生に深く関わる神様として、神話には高木神や高木大神などの神名でも登場します。
古事記では、天地開闢のときに天之御中主神に続いて、高御産巣日神が高天原に現われました。
目次
高御産巣日神の読み方と意味
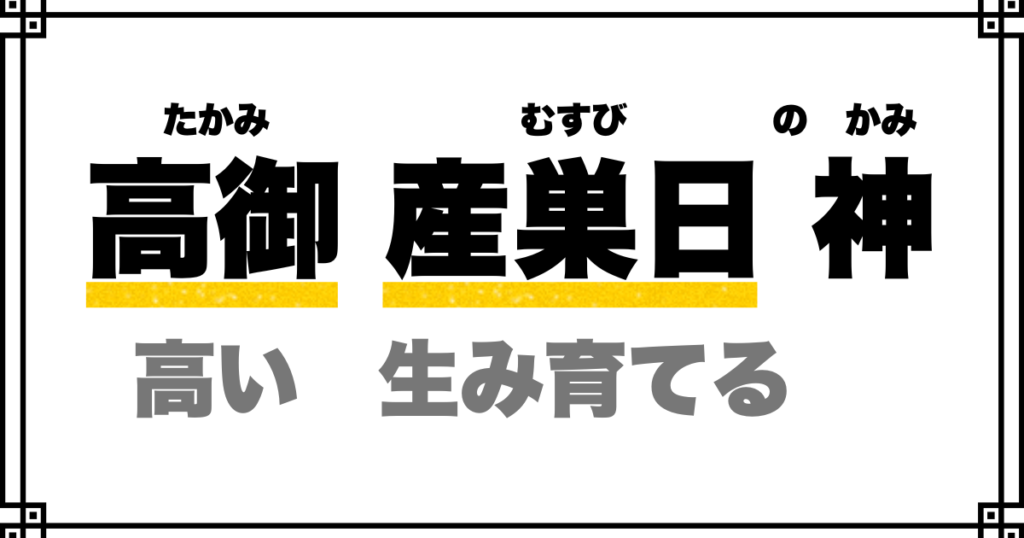
高御産巣日神の読み方は「たかみむすびのかみ」で、生命の誕生に関わることから「高く生み育てる」といった意味をもつ神名です。高木大神としても知られており、樹木に宿る神様といったイメージがあります。
神話のなかの高御産巣日神
『古事記』および『日本書紀』に登場する高御産巣日神について紹介します。
古事記における高御産巣日神
『古事記』では、第一章「世界の始まり」第一文で天地開闢のときを書き、天之御中主神の次に高御産巣日神が現れたと記述しています。
日本書紀における高御産巣日神
『日本書紀』の本文では、造化の三神への言及がありませんが、顕宗天皇の発言として「我が祖神に天照大神と高御産巣日神がおられる」との一文があります。
造化の三神と高御産巣日神
高御産巣日神は、天地開闢のときに現われた天之御中主神、神産巣日神と共に、造化の三神に含まれる神様です。また、神世七代よりも前に現われた別天津神でもあります。
姿形はなく、性別や夫婦関係のない独り神で、高天原に現われてからスグに隠れられました。
高御産巣日神を祀る神社
高御産巣日神のみを祀る神社は見当たらず、造化の三神をそろって祀る神社が日本各地にあります。
伊勢神宮を中心とした天照大神を祀る神社が多いなか、高御産巣日神など造化の三神や神世七代の神々を祀る神社は少ないため、皇室内でのみ祀られてきたという説や、地域ごとに祀られてきた氏神様を集める形で古事記成立時に創作された説などが見られます。