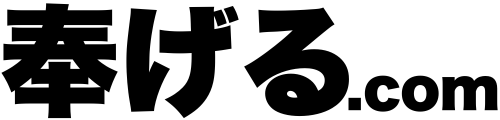祇園系神社とは、主に素戔嗚尊(すさのおのみこと)や牛頭天王(ごずてんのう)を御祭神とする神社の系統で、疫病除けや厄除けのご利益があることで広く信仰されています。祇園信仰は、平安時代に疫病を鎮めるために始まり、全国に広がりました。総本宮は京都の八坂神社で、その他にも代表的な神社として広峯神社(兵庫県)や津島神社(愛知県)などがあります。
祇園系神社とは
祇園系神社は、疫病や災厄を鎮めることを目的とした信仰から発展しました。もともとは仏教的な牛頭天王信仰と神道の素戔嗚尊信仰が融合した形であり、明治時代の神仏分離令後は素戔嗚尊を主祭神とする神道の信仰として定着しました。
祇園信仰の特徴
- 疫病除け・厄除け:平安時代の疫病流行をきっかけに発展。
- 全国に広がる信仰:八坂神社を中心に、全国各地に約2300社が存在。
- 祭礼と行事:特に有名なのが京都の「祇園祭」で、日本三大祭にも数えられます。
祇園系神社の御祭神
多くの祇園系神社では、以下のような神々が御祭神として祀られています。
素戔嗚尊(すさのおのみこと)
素戔嗚尊は、古事記や日本書紀に登場する荒ぶる性格を持つ神でありながら、疫病除けや厄除けの力を持つとされています。彼が新羅から出雲へ渡り、日本各地で崇敬されたことが伝えられています。
牛頭天王(ごずてんのう)
牛頭天王は元々インド由来の疫病を司る守護神であり、日本では素戔嗚尊と同一視されるようになりました。特に中世には牛頭天王信仰が広まり、多くの祇園系神社で崇敬されました。
祇園系神社のご利益
祇園系神社には主に以下のご利益があります。
疫病除け
平安時代から続く疫病除けの信仰は、現代でも重要な役割を果たしています。特に新型コロナウイルス感染症など現代の疫病にも関連して再び注目されています。
厄除け
素戔嗚尊や牛頭天王は厄災を防ぐ力があるとされており、多くの参拝者が厄年や人生の節目に訪れます。
家内安全・無病息災
家族や個人の健康、安全を守るために多くの参拝者が訪れます。特に「茅の輪」をくぐることで無病息災を願う風習があります。
祇園系神社に伝わる逸話や伝説
祇園系信仰には多くの逸話や伝説があります。特に有名なのは、素戔嗚尊が貧しい蘇民将来命を助けたという話です。この逸話から、「蘇民将来子孫也」と記された護符が災厄避けとして用いられるようになりました。
祇園系神社の総本宮と代表的な神社
| 系統名 | 総本宮 | 代表的な神社 |
|---|---|---|
| 八坂系 | 八坂神社(京都) | 広峯神社(兵庫)、津島神社(愛知)、須佐神社(島根) |
| 広峯系 | 広峯神社(兵庫) | 素盞嗚神社(兵庫)、八雲神社(島根) |
| 津島系 | 津島神社(愛知) | 天王神社(愛知)、須賀神社(島根) |
八坂系では京都市内で行われる「祇園祭」が最も有名ですが、それ以外にも各地で独自のお祭りや行事が行われています。
祇園系神社の主な例祭や行事
祇園祭
毎年7月に京都で行われる「祇園祭」は、約1ヶ月間続く大規模な祭礼です。山鉾巡行など華やかなイベントが行われ、日本三大祭りとしても知られています。
天王祭
各地の津島信仰では「天王祭」が行われます。これもまた疫病退散を願うお祭りで、多くの場合夏季に開催されます。
祇園系神社まとめ
- 御祭神:主に素戔嗚尊と牛頭天王。
- ご利益:疫病除け、厄除け、家内安全。
- 総本宮:京都・八坂神社。
- 代表的な例祭:京都・祇園祭、各地の天王祭。
全国各地に広がるこの信仰は、現在でも多くの人々から厚い信仰を集めています。