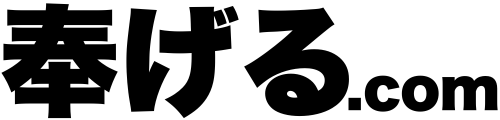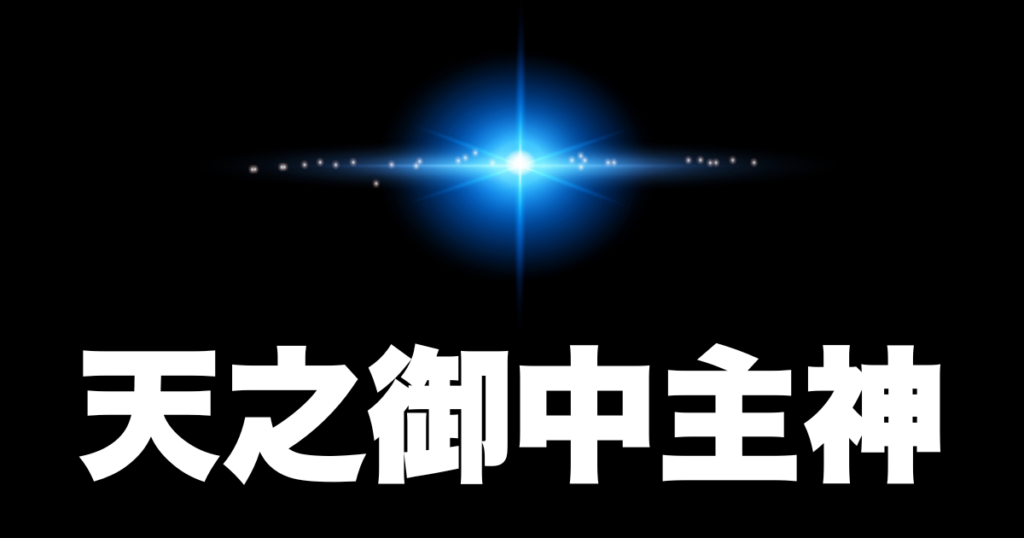「天神五柱から神世七代まで」は、古事記の上巻の神話の冒頭、天地開闢から伊邪那岐神(いざなぎのかみ)と伊邪那美神(いざなみのかみ)の登場までを描いています。
天と地が最初に現われたときに、高天原(たかまのはら)で現れた神の名は、天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)です。その後に続く神々は、高御産巣日神(たかみむすびのかみ)と神産巣日神(かみむすびのかみ)です。この三柱の神々は、いずれも独りで現れて、姿を隠しました。
次に、国がまだ若く、浮かぶ脂のようであり、葦の芽が萌え出るような状態の時に現れた神々について述べています。
まず、宇摩志阿斯訶備比古遅神(うましあしかびひこぢのかみ)が現れ、その後に天之常立神(あめのとこたちのかみ)が続きます。この二柱の神もまた独りで現れて、姿を隠しました。これら五柱の神々を「別天神(ことあまつかみ)」と呼びます。
次に現れた神々は、国之常立神(くにのとこたちのかみ)と豊雲野神(とよくものぬしのかみ)です。この二柱もまた独りで現れて、姿を隠しました。
その後に続く神々は、宇比地邇上神(うひじにのかみ)と妹須比智邇去神(いもすひじにのかみ)、角杙神(つぬぐいのかみ)と妹活杙神(いきぐいのかみ)、意富斗能地神(おおとのじのかみ)と妹大斗乃辨神(おおとのべのかみ)、於母陀流神(おもだるのかみ)と妹阿夜訶志古泥神(あやかしこねのかみ)、そして伊邪那岐神(いざなぎのかみ)と伊邪那美神(いざなみのかみ)です。
国之常立神から伊邪那美神までを「神世七代」と呼びます。最初の二柱は独りで現れ、それぞれを一代とします。次に続く十柱は二柱ずつ対になって現れ、それぞれを一代と数えます。