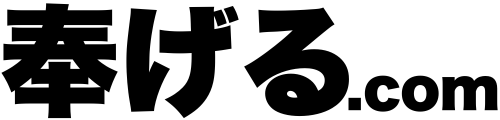恵比寿系神社とは、主に「恵比寿神(えびす)」を祀る神社の系統で、商売繁盛や漁業・海運の守護神として古くから信仰されています。恵比寿神は七福神の一柱で、日本古来の福の神として親しまれています。特に関西地方では「えべっさん」などの愛称で広く知られ、商人や漁師を中心に強い信仰を集めています。恵比寿系神社には大きく分けて「蛭子神(ひるこ)」を祀るものと、「事代主命(ことしろぬしのみこと)」を祀るものの二系統があります。
総本宮は、蛭子神系では兵庫県西宮市にある「西宮神社」、事代主命系では島根県松江市にある「美保神社」です。また、全国には3,500以上の恵比寿系神社が点在しており、日本三大えびすとして西宮神社、美保神社、京都ゑびす神社が知られています。
恵比寿系神社の御祭神
多くの恵比寿系神社では、以下の2柱を中心に祀っています。
1. 蛭子神(ひるこのかみ)
蛭子神は、イザナギとイザナミの間に生まれた最初の子供で、体が不完全だったため舟に入れて流されました。その後、漁業の守護神として信仰されるようになり、特に海運や漁業関係者から厚い信仰を集めています。
2. 事代主命(ことしろぬしのみこと)
事代主命は、大国主命の子であり、国造りに貢献したとされる神です。釣りをしていた逸話から、大漁や商売繁盛の守護神として崇敬されています。特に美保神社では事代主命が主祭神として祀られています。
恵比寿系神社のご利益
恵比寿系神社の主なご利益は以下の通りです。
1. 商売繁盛
恵比寿神は商売繁盛の守護神として広く信仰されています。特に関西地方では「十日戎(とうかえびす)」という祭りが行われ、多くの商人が参拝します。
2. 大漁・海運安全
漁業関係者からも厚い信仰を集めており、海運や漁業における安全と繁栄を祈願するために多く参拝されます。
3. 家内安全
家族全員が健康で平穏な生活を送れるよう祈願するためにも、多くの人々が恵比寿系神社を訪れます。
恵比寿系神社に伝わる逸話や伝説
恵比寿神には多くの伝説があります。例えば、蛭子神が流された後、漁師によって拾われて漁業の守護神となったという話があります。また、事代主命が釣りをしていた際に大魚を釣り上げ、それが大漁祈願につながったという逸話もあります。
恵比寿系神社の総本宮と代表的な神社
| 系統 | 神社名 | 所在地 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 蛭子(ヒルコ)系 | 西宮神社 | 兵庫県西宮市 | 全国約3,500社ある蛭子系えびす社の総本宮 |
| 事代主命(コトシロヌシ)系 | 美保神社 | 島根県松江市 | 全国約3,000社ある事代主命系えびす社の総本宮 |
| その他代表的なえびす社 | 京都ゑびす神社 | 京都府京都市東山区 | 商売繁盛祈願で有名な「十日ゑびす」祭り |
恵比寿系神社の主な例祭や行事
十日戎(とうかえびす)
毎年1月10日前後に行われる商売繁盛のお祭りです。9日が「宵戎」、10日が「本戎」、11日が「残り福」と呼ばれ、多くの参拝者が福笹などを求めて訪れます。特に西宮戎や今宮戎では数十万人以上が参拝する大規模な祭典です。
美保関祭
美保関で行われる例祭で、海運安全や大漁祈願を目的とした祭りです。船舶関係者や漁師たちが多く参拝します。
恵比寿系神社まとめ
恵比寿系神社は、日本全国で信仰されている商売繁盛や海運安全、大漁祈願など多岐にわたるご利益を持つ重要な存在です。特に西日本では強い信仰基盤を持ち、「えべっさん」の愛称で親しまれています。また、その歴史的背景には蛭子と事代主命という二つの異なる起源があり、それぞれ異なる地域性や文化的特徴を持っています。