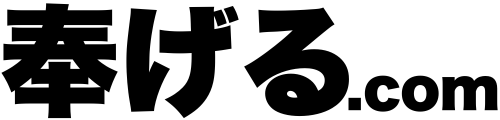日吉系神社とは、主に大山咋神(おおやまくいのかみ)を御祭神とする神社の系統で、厄除けや方除けのご利益があることで広く信仰を集めています。全国に1724社存在し、その総本宮は滋賀県大津市にある日吉大社です。代表的な神社としては、日枝神社(東京都)、新日吉神宮(京都府)、日吉八幡神社(秋田県)などが挙げられます。
日吉系神社とは
日吉系神社は、比叡山の守護神として崇められてきた大山咋神を祀る神社群であり、古くから天台宗との深い関わりを持っています。特に平安京の鬼門に位置することから、国家鎮護や方除けの信仰が厚く、朝廷や武士階級からも篤く信仰されてきました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 総本宮 | 日吉大社(滋賀県大津市) |
| 御祭神 | 大山咋神、大己貴神など |
| ご利益 | 厄除け、方除け、開運 |
| 代表的な神社 | 日枝神社(東京)、新日吉神宮(京都)、日吉八幡神社(秋田) |
| 神仏習合 | 天台宗と深い関わり |
日吉系神社の御祭神
多くの日吉系神社では、主に2柱の御祭神が祀られています。以下、それぞれについて詳しく解説します。
大山咋神(おおやまくいのかみ)
大山咋神は比叡山を守護する地主の神であり、古事記にもその名が記されています。彼は山の神でありながら農業や豊穣を司る側面も持ち合わせています。特に比叡山延暦寺との結びつきが強く、天台宗の護法神としても崇敬されています。
大己貴神(おおなむちのかみ)
大己貴神は、大国主命とも同一視される国土開拓や医療、縁結びの神です。奈良県三輪山から勧請されたこの神は、国家鎮護の役割を担い、大津京遷都時には特に重要視されました。
日吉系神社のご利益
日吉系神社には多様なご利益がありますが、主なものは以下の3つです。
厄除け・方除け
日吉系神社は平安京の鬼門を鎮護するために祀られた背景から、厄除けや方除けに特化しています。特に家屋や土地の厄災を防ぐために参拝する人々が多いです。
開運・商売繁盛
大山咋神は農業や豊穣を司るため、新しい事業や商売繁盛にもご利益があります。また、大己貴神も国土開拓の象徴であるため、新たな挑戦や事業開始時に参拝されることが多いです。
縁結び・健康長寿
大己貴神は縁結びや医療にも関わるため、人間関係や健康面でのご利益も期待されています。特に縁結びでは、多くの参拝者が訪れます。
日吉系神社に伝わる逸話や伝説
日吉大社には多くの伝説があります。その一つとして、大山咋神と大己貴神が出会ったという伝承があります。この二柱が出会った場所とされる岩が比叡山にあり、それが縁結び信仰にも繋がっています。また、「猿」が魔除けとして崇められており、「魔が去る」として厄払いの象徴とされています。
日吉系神社の総本宮と代表的な神社
全国の日吉・日枝・山王系統の総本宮は滋賀県大津市の日吉大社です。この他にも各地に有名な日吉系の神社があります。
| 神社名 | 所在地 | 特徴 |
|---|---|---|
| 日吉大社 | 滋賀県大津市 | 総本宮。方除け・厄除けで有名 |
| 日枝神社 | 東京都千代田区 | 江戸城鎮護として徳川家康が祀った |
| 新日吉宮 | 京都府京都市 | 平安京遷都時に創建された古い歴史 |
日吉系神社の主な例祭や行事
日吉大社では毎年4月に「山王祭」が行われます。この祭りは湖国三大祭りの一つであり、勇壮な宵宮落しなど多彩な行事が展開されます。また、各地の日枝・日吉系統でも例祭が行われ、多くの参拝者で賑わいます。
日吉系神社まとめ
日吉系神社は、大山咋神を中心とした厄除け・方除け信仰を基盤とし、日本全国に広まった重要な信仰体系です。その総本宮である日吉大社は比叡山延暦寺との深い関わりを持ち、日本史上でも重要な役割を果たしてきました。